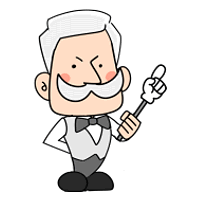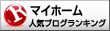このサイトをご覧頂いている読者のみなさんは「これから注文住宅でマイホームを建てよう!」と検討している方が多いと思います。
自由設計の注文住宅で夢のマイホーム計画。上手くいけばこれほど楽しく充実することはありません。ですが自由設計の注文住宅だからこそ難しい問題に直面することもあります。
注文住宅を建てる施主のほとんどが頭を悩ませる問題。それは「間取り」です。
間取りは家の「生活のしやすさ」を決める最重要ポイントです。一から自由設計できるからこそ「どの間取りが自分にとって最適解なのか?」という難問が施主を悩ませます。
もちろん注文住宅を建てる以上、専任の建築士などが担当して希望のプランに合う提案をしてくれますが、その提案力(プラン力)はハウスメーカーでレベルが異なりますし、担当者レベルでもバラつきがあります。
ですから、施主サイドにも最低限の間取りと生活動線の知識があるに越したことはありません。
施主サイドに必要な知識がなければ、夢のマイホームプランを営業マンサイドに握られてしまい、希望のプランが実現できなくなってしまう可能性もあり得ます。
マイホーム作りは営業マンに主導権を握らせるのではなく、常に施主であるあなたが主導的な立場であるべき。
こちらに間取りや生活動線の知識があれば、もしもハウスメーカーの担当者が的外れな提案をしてきた場合は毅然と意見を言えますし、そもそも的外れな提案をするハウスメーカーは選択肢から外してしまえばいいのです。施主サイドに間取りや生活動線の知識があれば提案力の高いハウスメーカー選びにも必ず役立つはずです。
マイホーム購入は一生に一度の特別な買い物です。絶対に失敗しないために最低限の間取り・生活動線の知識を身につけておきましょう。
このページではこれから家を建てる方のために、失敗しない間取り生活動線の最低限の知識をまとめます。注文住宅を検討している方はもちろん、建売住宅の購入を検討している方やマンション購入を検討している方にも是非見ておいて頂きたい内容となっております。
少し長くなりますが、できるだけ要点だけをまとめてコンパクトにまとめますのでどうぞご一読ください。
Contents
まずは現在の家の不満な点・満足な点を書き出してみよう!
まず注文住宅の間取りを考えるうえで、現在住んでいる家の間取りを思い浮かべてみましょう。そして、現在の家の不満な点を書き出してみると良いです。現在の家の不満な点を書き出し、同じ不満を抱くことがないように新たな家では対策しておくことが大切です。
また不満点と同様に現在の家で「満足している点」も書き出してみるといいでしょう。満足している点は、出来る限り変えないような間取り・生活動線を考えるべきです。この点はむしろ不満な点よりも重要です。
現在の家で満足している点が、新築したマイホームで叶えられていなかった場合、「前の家の方が良かった…」ともなりかねません。せっかく注文住宅でマイホームを建てるのに、そんなことは絶対に思いたくないですよね。
不満な点の例
・コンセントの数が足りない
・収納が少ない・狭い
・玄関がせまい
・他人の目線が気になってカーテンが開けられない
・日当たりが悪い
満足な点の例
・水周りがまとまっていて便利
・バルコニーが広い
・天井が高くて開放感がある
・キッチンシンクが広く使いやすい
このように現在の家のいいところ、悪いところを書き出しておくと次の新居の間取りに活かせます。現在の家の状況を自分で把握しておくことはかなり大切ですよ。
そんなに時間がかかる作業ではありませんので、注文住宅を建てる場合は必ず「現在の家の不満点・満足点」を書き出して新居の間取りプラン決めにフル活用しましょう。
「自分の理想の間取りがわからない…」こう思う方もいると思います。そんな方は10社くらいの住宅カタログ取り寄せて、掲載されている「間取り実例」のなかから気にいったものをスマホのカメラでけっこうですので撮っておいてください。
気に入った間取りプランがいくつか溜まれば自分の好みの傾向がわかるはずです。また間取り写真をハウスメーカーの担当者に見せてプロの意見を聞くこともできますし、ハウスメーカーごとに間取りの提案力をみることもできます。
住宅カタログにはたくさんの間取り実例が掲載されていますので、まずは直感でいいので自分の理想の間取りをたくさん撮り貯めて比較検討してみましょう。
注文住宅のはじめの一歩!まずはココから無料カタログを比較しよう!
希望の間取りや条件に優先順位を付けよう!
間取りだけに限った話ではありませんが、注文住宅を建てる際には「希望の条件に優先順位を付ける」というのも重要です。夢だったマイホーム計画です。いざ、計画してみるとこだわりたい箇所がこれでもかと出てくると思います。また、ご夫婦の場合はパートナーと意見が合わないということもしばしば。
正直な話、注文住宅は間取りやデザイン性はもちろん、耐震性や断熱性などの機能面なども無数の選択肢がありこだわりだすとキリがありません。
「予算は際限なし!いくらかかっても構わない」という金銭的余裕がある家庭以外は全ての要望を取り入れることは「ほぼ不可能」だと考えておいた方がいいです。家族全員、全ての要望を取り入れるとなると間違いなく「予算オーバー」になります。
予算を超えてしまって、あわててどの部分でコストカットをしようか考えていると考えがボヤけてしまい大切な部分を削ってしまうことにもなりかねません。
希望の間取りや条件に「優先順位」を付けておき、絶対に外せない条件と場合によってはあきらめてもいい条件を予めしっかりと把握しておくことがオススメです。こうすることで担当の建築士もプランを立てやすくもなります。結果的に注文住宅のプラン決めがスムーズに進みますよ。

注文住宅で失敗しやすい間取りや生活動線
初めての注文住宅で失敗しないために、これまでに家を建てた人が「どんなところで失敗しているのか?」を把握しておくことも大切です。
注文住宅でよくある「生活動線」「水まわり」「リビング周り」「コンセント周り」「収納」の失敗にフォーカスし具体例な失敗例も挙げていきますので、マイホームを建てた諸先輩方と同じ失敗をしないよう注意しましょう。
生活動線の失敗例
・1階に洗濯機置き場を配置して失敗。洗濯の度に2階バルコニーの物干しに階段をのぼることに
・1階に手洗い場を配置せず失敗。帰宅のたびに2階までのぼることに
・お風呂を2階に配置して失敗。子どもが汚れて帰宅した時はリビングまで汚れてしまう
・トイレの位置で失敗。寝室から遠くて夜中にトイレで起きた時が面倒
・キッチンと洗濯機のフロアを分けて失敗。料理をしながらの家事がやりにくい
- 間取りプランは生活動線を考えてから!
自由設計の注文住宅で必ず考えておきたいのが生活動線です。生活動線とはリビング、寝室、キッチン、洗面所、トイレなど家の中で行き来する「線」のことです。
家の間取りを決める際は生活動線を考えておかなければ必ず失敗すると言っても過言ではない重要ポイント。
生活動線が複雑な線だったり、何度も重なりあったりするのは良い生活動線とは言えません。シンプルな線で繋げられるのが良い生活動線です。
例えば洗濯機が1Fにあって2Fのバルコニーまで干しに上がって1Fの居室のクローゼットにしまうのは面倒ですよね。このように家事を行うために何回も家の中を行き来しなければならない間取りは生活動線が良いとは言えません。
生活動線が良い家と悪い家は住み心地が全く変わってきますので、予め生活動線を考えて間取りプランを設計するようにしましょう。
設計担当者から間取り図のプランを貰ったらその図面に生活動線を書きこんでシンプルな線で繋がるかどうかを試してみることが大切です。
- 水まわりは固めて配置が基本
生活動線は特に水まわりの位置が大きく関係します。水まわりとはキッチン・洗濯機・洗面所・お風呂など住宅のなかで水を使う箇所のこと。
水まわりの配置を失敗して、家事動線の悪い家になってしまうケースも多いです。家事をする際の生活動線にきわめて大きく影響する設備ですので、しっかり考えておくのがオススメです。
基本的にキッチン、洗面所、洗濯機、お風呂などの水まわりは「まとめて配置するのが基本」と覚えておきましょう。
特に洗面所・洗濯機・お風呂などの水まわりはまとまっていると生活動線が便利になります。お風呂から出てその場でドライヤーやお化粧などができますし、お風呂の残り湯を洗濯機に活用することも可能です。またこれらの水まわりがまとまっていれば配管工事や設備の取り付けも比較的容易になり、配管距離を抑えられ結果的にコスト削減にも繋がります。
洗濯機とキッチンの距離を近づけておくとキッチンで料理をしながら洗濯機を回すなど家事を同時に行うのもラクになります。
失敗しがちなのが洗濯機が1Fにあるのに、物干し竿が2Fのバルコニーにしかないというケース。これは洗濯モノを干すたびに階段を上らなくてはいけないので、家事がおっくうになってしまいがちな生活動線です。できるだけ洗濯機と物干しスペースは近づけておくのがベターでしょう。
- 水まわりなどの設備は建物の裏側にまとめる
基本的に水まわりなどの設備は建物の裏側にあたる部分に配置するのがオススメです。住宅というの多くの場合オモテ側にスペースを十分にとってあるもので日当たりも良いケースが多いです。裏側は隣地との距離が近かったり日当たりが悪いケースが多いですが、そういう場合は迷わず水まわりを裏側に配置しましょう。
お風呂・洗面所・脱衣所・トイレなどは基本的に日当たりが悪くても問題ないですし、むしろ人目につきたくない場所なので視線が遮られる裏側に配置するのがベストです。また水まわりには給湯器や各種メーターなどの設備機器が付随します。こういった設備機器を裏側にまとめて配置できるので、オモテ側がスッキリして見栄えもよくなります。
日当たりが良いオモテ側にはリビングダイニングや居室などくつろげるスペースを配置するのが良い間取りのセオリーです。
トイレ位置の失敗例
・トイレをリビングの隣に配置して失敗。気配や音が気になる
・寝室の真上にトイレを配置して失敗。夜中、トイレの流水音で目が覚める
・寝室と遠い位置にトイレを配置して失敗。夜中のトイレが面倒
- トイレは近すぎず離れすぎずを意識しよう!
トイレの位置に悩む方は多く、実際「トイレの配置に失敗した」という実例も多いです。
例えばトイレをリビングやダイニングキッチンの真横に配置してしまって後悔しているという声はけっこう多いです。確かにリビングからドア1枚挟んですぐトイレだときまずいかもしれませんね。お食事中のトイレなど双方が気にしてしまうかもしれません。
また寝室の真上にトイレを配置して失敗したというケースもよく聞きます。寝室の真上にトイレを配置してしまうと、夜中にトイレを流す音で起きてしまうことがあるかもしれません。生活音のトラブルはストレスの元ですのでできるだけ寝室の真上にトイレを配置するのは避けたほうがいいかもしれません。
逆にリビングや寝室から遠い位置にトイレを配置してしまい後悔するケースもあります。リビングは家の中でもっともくつろげる空間ですので、必然的に滞在時間が長いです。例えばリビングから階段を上り下りしないとトイレに行けないとなるとちょっと不便ですよね。
また寝室からトイレが遠いのもちょっと不便です。眠いなか長い距離を歩いてトイレにいってまた長い距離を歩いて寝室に戻るのですから、人によってはそれだけで目が冴えてしまって眠れなくなるかもしれません。
トイレはリビングや寝室から近すぎず遠すぎずの中間距離に配置するのがベターでしょう。
リビングの失敗例
・1階リビングにして失敗。日当たりが悪い家になってしまった
・1階リビングにして失敗。人の目が気になりカーテンが開けられない
・2階リビングにして失敗。夜中、家族の足音で眠れない
・2階リビングにして失敗。買い物のたびに荷物を2階まで運ぶのが面倒
・2階リビングにして失敗。夏は暑くなりエアコンなしではいられない
・リビングを吹き抜けにして失敗。2階が狭くなってしまった
・リビングの天井を高くして失敗。夏も冬もエアコンの効きが悪い
・リビングをダウンフロアにして失敗。高齢の両親は段差が苦手
- 1Fリビングと2Fリビング結局どちらがいいのか?
注文住宅を建てる時に誰もが迷うのが、家の中心的位置になるリビングの配置です。リビングは1Fに配置するのがいいのか、それとも2Fに配置するのがいいのか頭を悩ます方が多いです。
リビングは「家族が集まるくつろぎの空間」であり、家のなかでもっとも滞在時間の長い空間です。家のどこにリビングを配置するかで過ごしやすい家かそうでないかを左右すると言っても過言ではありません。
正直なところ1Fと2Fのどちらにリビングを配置した方がいいのかは、それぞれの住宅の敷地条件や周辺の状況によって異なるため一概にはいえません。どちらにもメリット(長所)・デメリット(短所)があるからです。
この項目では1Fリビングの方が良いケース、2Fリビングにした方が良いケースをまとめます。
- 採光が取れるならリビングは1Fがベター
結論から述べてしまいますが、広い土地が確保できる場合や1階でも日当たりが良い、人目が気にならない敷地条件である場合はリビングは1階に配置するのが基本形でしょう。
1階リビングの最大のメリットはなんといっても「2階に上がる必要がない」というところです。
単純な理由ですが、買い物から帰ってきて重い荷物を2階まで運ぶ必要がないのは長く住む家を想定すると非常に重要なポイントです。また1階にリビングを配置すれば2階に上る回数が減りますので、年をとり体力がおちた時のことを考えてもラクです。
またお子様がいる場合などは1階リビングの場合、帰宅・外出などの出入りがわかりやすいのもメリットです。他にも家族で就寝時刻がバラバラの場合、2階リビングだと寝室に足音が響いてしまうというデメリットがあります。1階リビングなら寝室に足音が響くことがありませんので、その点も安心でしょう。
「お庭」「テラス」がある場合は断然1階リビングでしょう!リビングの先に外部空間であるテラスがあると、家の中と外の境界線があいまいになり視覚的に非常に広く感じ開放感のあるリビングになりやすいです。
1階リビングの最大のデメリットは都市部など住宅が密集している地域の場合「日当たりが確保しにくい」という点と、道路などに面している場合は「人の目が気になる」という点でしょう。2階リビングを選択する人はこれら2点がクリアできていないケースがほとんど。
つまり逆に言えば「日当たり」「人の目」の2点をクリアできている場合は1階リビングには大きなデメリットはないと言えます。
- 採光が厳しいなら2Fリビングという選択肢
では2階リビングは良くないのか?と言われるとそういうわけではありません。2階リビングにも良いところはたくさんあります。
確かに、2階リビングを選択する人は「1階だと日当たりが悪いから」「1階だと人目が気になるから」という、いわば消去法的な理由で選択する人が多いのは事実ですが、実は2階リビングにもいいところは多数あります。
1階に比べて「日当たりが良い」「人の目が気にならない」「眺望が良い」という理由はもちろんですが、他にも2階リビングは「耐震性能が向上する」という副産物的なメリットもあります。一般的に柱や耐力壁の数が多ければ住宅の耐震性能は上がりますので、1階にドーンと開放的なリビングがあるよりも、1階に柱や壁によって間仕切りされた居室がある方が耐震性能は高まります。
また2階リビングでもに広めのルーフバルコニーが繋がっていれば開放感のあるリビングとなります。むしろ1階よりも眺望が良く風通しも良いので1階リビングよりも開放感の面では上かもしれませんね。
正直なところ、1階リビングにも2階リビングにもメリット・デメリットがあるため、最終的には好みの問題になってしまいます。以下にわかりやすく箇条書きで1階リビング・2階リビングの特徴をまとめておきますので、特徴をよく把握したうえで家族間で話し合うとよいでしょう。
1Fリビングのメリット(長所)
・2階に上る必要がない
・子どもがいる場合、出入りがわかりやすい
・庭・テラス・縁側があれば非常に開放感がある
1Fリビングのデメリット(短所)
・日当たりが遮られる
・人目が気になる
2Fリビングのメリット(長所)
・日当たりが良い
・風通しが良い
・人目が気にならない
・眺めがいい
・耐震性能が向上
・ルーフバルコニー・デッキテラスがあれば非常に開放感がある
2Fリビングのデメリット(短所)
・2階に上る必要がある
・夏は暑くなりがち
・1階に寝室がある場合、夜家族の足音が気になる
- 吹き抜け・天井高には要注意
注文住宅でマイホーム計画。多くの人にとっては一生に一度の特別高額な買い物ですからデザイン性にもトコトンこだわりたいものですがデザイン性にこだわり過ぎて、肝心の機能面がおろそかになってしまうこともあることを覚えておきましょう。
特にリビングのデザイン性を大きく変化させる「吹き抜け」や「高い天井」「ダウンフロア」などには少し注意が必要です。
例えば吹き抜けは広々と開放的な空間を演出し家の印象をガラリと変えますが、デザイン性が高まる代わりに夏でも冬でも「エアコンの効果」は弱まります。また、吹き抜けというのは「本来あるべき2階の部屋を取り払う」のと同義です。家全体の総床面積が減るというデメリットもあります。
「天井を高くした場合」やリビングの床を一段下げた「ダウンフロア」も、開放感があり居心地の良い空間になる代わりにエアコンの効きは弱まります。ダウンフロアは年をとった時にバリアフリーの面でもビハインドとなるかもしれません。
天井の高い家もダウンフロアリビングもデザインの面では非常にかっこいいですし、居心地の良い空間になるのですが、デザインのこだわりすぎには注意。デザイン性に凝りすぎて機能面がおろそかになったり、逆に暮らしにくい家になってしまう可能性もあるのです。
いずれにしても「吹き抜け」」や「高い天井」「ダウンフロア」は、高い断熱性能を誇る家であることが前提条件です。断熱面で問題ないのであれば非常に魅力的な家になると思いますよ。
基本的に「住宅においてデザイン性と機能性は相反するもの」と考えておくべきかもしれません。
もちろんせっかく自由設計の注文住宅ですからデザイン性はある程度は重視するべきですが、バランスを考えてこだわっても問題の無い部分なのかどうかは常に意識しておくべきです。デザイン性は「ほどほどにこだわる」くらいがちょうど良さそうです。
コンセントの失敗
・コンセントの個数で失敗。年々家電が増えてコンセントが足りなくなった
・コンセントの位置で失敗。延長コードなしでは家電が使えない
- コンセント・スイッチは生活動線や配置する家電に合わせて
注文住宅においてコンセントやスイッチの失敗も非常に多いです。近年では使用する家電製品も増加傾向にありますので、必然的にコンセントの数も増加されている傾向にあります。
せっかくのマイホーム。延長コードやタコ足コンセントは少し不格好ですし、できることなら使わずに生活できるのがベストです。
コンセントやスイッチ類で失敗しないためにはまずは新居で使用する家電の数、配置を想定することが必要不可欠です。家具、家電の配置を想定し、さらに生活動線も想定するとさらに良いです。そして、できればその想定した家電の数よりも1~2口多めの口数を確保しておきたいところです。
家電はこれからドンドン増えてくるかもしれませんし、家族が増える可能性も考慮すべき。それにコンセントに余裕があればお部屋の模様替えの自由度も格段に高まります。コンセントは多いに越したことはありません。コンセントを規定の数よりも増やせば、当然その分はオプション料金となり初期費用はかさんでしまいますが、コンセントは後から増設した方が費用がかかります。
たかがコンセントといえど、生活動線にも密接に関わってくる部分ですのでしっかりと考え、少し余裕をもった個数を付けておくことをオススメします。
収納の失敗例
・収納が足りない…
・収納の奥行きで失敗。奥行きを深くしすぎて出し入れしにくい
・壁面収納を作り過ぎて失敗。家具を寄せておける壁面がない
収納もお家の間取りの悩みポイントの一つです。収納の失敗例もよく聞く話ですね。
一般的に収納面積は延べ床面積の15%~20%くらいが必要と言われています。
ただし、収納がどれくらい必要なのかは人によってかなり差が大きい部分ですので、まずは自分の生活スタイル・荷物の多さを把握することが大切です。また、収納もコンセント同様に将来家族が増えた場合のことも考え、余裕のある収納スペースを確保しておくのが理想的です。
- 出し入れしにくい収納に注意
収納の失敗例で多いのが、収納スペースの広さは十分に確保したものの「しまいにくい」「出しにくい」といったケース。基本的に収納は床面積の広さよりも壁面積が重要です。
ただ床面積が広いだけの収納の場合、工夫しないと収納力が低くなってしまったり使い勝手が悪くなる可能性もあります。以下の図のウォークインクローゼットのように収納の壁面の面積が大きいとモノがたくさんしまえて、なおかつ中に入って出し入れできるため使い勝手も良い収納となりやすいです。
※ウォークインクローゼットの図
また奥行きがあり過ぎる収納は、収納力はありますが出し入れしにくくなる可能性が高いので注意が必要です。奥行きがある収納を作る時はウォークインクローゼットのように壁面を多く確保するのがオススメです。
- 壁面収納はつくり過ぎに注意
基本的に収納はたくさんあるに越したことはありません。収納を増やしたい時に役立つのがお部屋の壁一面を収納にする「壁面収納」です。壁自体が収納になるので非常に収納力が高まるので採用する住宅も多いですが、壁面収納もつくり過ぎると失敗のもとです。
壁面収納をつくり過ぎて、お部屋のほとんどの面がドア、窓、壁面収納のいずれかがある場合、テレビやソファなど家具や家電を寄せて配置するスペースがなくなってしまいます。壁面に寄せておける場所がないと非常に落ち着かないお部屋になってしまいがち。
なにごとも「過ぎたるは及ばざるがごとし」です。お部屋の壁は1面か2面はなにもない面があるのがオススメです。
まずは、新居での生活を想定して家具をお部屋のどこに配置するかもシミュレーションしておくと良いでしょう。
デッドスペースの失敗例
・長い廊下で失敗。廊下が長くて居室が狭い家になってしまった
・階段の下がデッドスペースになり失敗。せっかくだし有効活用できるようにすれば良かった
失敗しないための間取り計画。デッドスペースはできるだけ少なくすることが失敗しない間取りのコツです。
- 廊下はできるだけ短く
例えばデッドスペースになりやすい場所といえば廊下です。できるだけ廊下は短くなるような設計をお願いするとその分、リビングやお部屋を広くすることができます。廊下の幅が狭すぎるのも問題ですが、廊下の長さはできる限り短くした方が空間を有効活用できます。
どうしても廊下が長くなってしまう場合もあると思いますが、ならば廊下に壁面収納を付けるのも一つの手です。廊下には特段置くべき家具はありませんし、収納にするのはオススメです。
- 階段下のデッドスペースを有効活用
また階段の下部分もデッドスペースになりやすい空間と言われています。階段下のデッドスペースを有効活用できれば、これまた家の中の限られた空間を有効活用することができます。もともと広い敷地が用意できる場合以外は、通常デッドスペースになりがちな階段下を有効活用するプランを考えるのもオススメです。
具体的な階段下の有効活用方法として、一般的な箱型階段の場合にもっとも主流なのは「収納スペース」として活用する案ですね。階段下はどうしても天井が低くなりがちですが収納として活用するのであれば天井高は低くても問題ありません。もっとも活用しやすい方法です。
また箱型階段の場合は階段下をトイレとして活用するケースもありますね。階段下にトイレを配置するのは、風水的にはあまり良くないとされているようですが、風水を気にしない人ならアリだと思います。トイレは基本的に座る場所ですし、天井が斜めになっていてもあまり気になりません。
またスケルトン階段の場合は収納家具を設置することで収納スペースとして活用することもできますが、他にもベンチを置いて腰かけスペースとして活用したり、デスクを置いて簡易的なパソコン作業コーナーとすることもできるかもしれません。
通常、デッドスペースとなりがちな階段下ですがアイディア次第ではオシャレに有効活用できるかもしれませんので、担当者さんに相談してみるのがオススメです。
階段下の有効活用方法 実例
・収納にする
・ベンチなどを置き腰かけスペースとして活用
・デスクを置きPCコーナーとして活用
・トイレにする
・テレビを置く
間取りのオススメテクニック
間取りや生活動線の具体的な失敗例をピックアップしてきましたが参考になったでしょうか。他にも少しだけ間取りのオススメテクニックを紹介していきます。
間仕切りのテクニック
間仕切りの多い家はプライバシーの確保には役立ちますが、堅苦しい・狭苦しいというビハインドもあることを覚えておきましょう。
水まわりやトイレなどのプライベートゾーンは間仕切りが必要ですが、リビングなどのパブリックな空間は必ずしも間仕切りが必要かというとそうではありません。時に間仕切りをなくすという選択肢ものびのびと開放的な空間作りに役立つかもしれません。
部屋の数は少なくなりますが、開放的でドーンと大きいリビングを作るには間仕切りを一つ無くすのも手です。
リビングなどは間仕切りの代わりに「引き戸」を設けるのもアリでしょう。引き戸であれば必要に応じて空間を仕切ることができ、来客時などには大空間のリビングに、普段はプライベートな空間にといった使い分けが可能です。
また引き戸ではなく半透明の間仕切りや格子戸という選択肢もあります。
「障子」など半透明の間仕切りは視線は遮りますが、音や気配などは感じますので閉塞感を感じにくい間仕切りです。また格子状の間仕切りも同様で、空間を完全に仕切るわけではありませんので適度に開放感を出すことが可能です。
ただし、間仕切りの少ない家は一つの空間が大きくなる代わりにエアコンの効きや断熱性能が弱点となります。のびのびとした大空間は「高い断熱性能」が大前提となることを覚えておきましょう。
回遊動線のテクニック
回遊動線と言う言葉をご存知でしょうか。回遊動線とは部屋などに2か所以上の出入り口をつくり、家の一部をぐるりと回遊できるようにした動線のことです。
例えば、水まわり・キッチン・収納・リビングを繋いだ動線が一つの円になるような間取りは回遊動線といえます。こういった回遊動線を確保することで生活動線をショートカットして短くできたり住宅の利便性が上がり、また家が広く感じると言われています。
重い荷物を持っている時なども回遊動線でショートカットできると便利ですし、お子様がいる家庭などはぐるりと遊びまわれるところがあるのは楽しいものです。もしも回遊動線を作れるようであれば作ってみるといいかもしれません。
軒下・縁側・ルーフバルコニーで開放感のある家に
軒下や縁側、ルーフバルコニーなどは住宅の開放感を倍増させる最高の空間です。軒下や縁側、ルーフバルコニーは家の中でもなく完全に家の外でというわけでもない「中間領域」。こういった中間領域がリビングなどと繋がっていることで、家の中と外の境界線があいまいになり家の中にいても半分外にいるような非常にのびのびとした開放的な空間を演出できます。
これはオープンカフェなどと同じ理屈ですね。こういう中間領域に憧れる人も多いと思います。もし広さにゆとりがあるながらオススメの間取りです。
ただし軒下・縁側・ルーフバルコニーは人の目が届かないことが前提条件。人目につくような場所ならば目隠しが必要不可欠です。目隠しをしても中と外が繋がる空間があると十分開放感はアップします。
天井高にメリハリを
「天井の高い家がいい!」
これは注文住宅でも多い要望の一つですが、全ての部屋・廊下を一律で天井を高くすると、やはりどこかでムダなスペースができてしまうもの。例えば特に収納やお風呂、洗面所などは特に天井が高くなくても問題ありません。
住宅のなかでもっとも滞在時間が長くくつろげる空間であるリビングの天井だけを高くし、その他の階は天井を低くしスキップフロアなどを設け空間を賢く利用するのも手です。
リビングや一部の居室だけ天井を高く、収納や水まわりなどの天井は低くメリハリのある天井高を設定することで天井の高い部屋がなおのこと広く感じるという効果もあります。
全ての部屋、全てのフロアで天井が高くなくても十分開放感のある家にできます。「賢く空間を利用したい」という旨を担当建築士に相談するのも良いでしょう。
眺望が良いならピクチャーウィンドウを
もしもあなた様が注文住宅を建てる場所が敷地条件的に「眺望が良いところ」ならばピクチャーウィンドウを配置するのもオススメです。ピクチャーウィンドウとはハメ殺しの窓の一種で、窓枠を額縁に見立てて外部の景色をまるで「絵画」のように取り込むインテリア窓のことです。
ピクチャーウィンドウは家の中のどこにあっても素敵な空間を演出してくれます。眺望や外の景色に自信がある敷地条件ならぜひ取り入れたいインテリアと言えるでしょう。
間取りをシミュレーションしよう!
間取りはとにかくシミュレーションすることが大切です。
注文住宅の設計担当の方が間取り図を印刷してくれる場合はできるだけ図面を複数枚もらうようにしましょう。生活動線を書きこんで生活をシミュレーションするためです。実際の生活をイメージして、線を書きこむことで間取りプランでの失敗は格段に減ると思います。
また、図面を作ってもらう前に自分で間取りをシミュレーションすることも大切です。現在はスマホアプリやPCのフリーソフトでも間取りをシミュレーションできるソフトが多数ありますので、そういったアプリやソフトで間取りをシミュレーションするのもオススメです。
失敗しない間取りや生活動線 まとめ
失敗しやすい間取り・生活動線の実例をピックアップしてみましたが、いかがでしたでしょうか。読者様の間取りプランの参考になれば嬉しい限りです。
よく「家は3回建てないと理想の家にはならない」と言われますが、間取りや生活動線で失敗しやすい点もこう言われる理由の一つです。事前に間取りや生活動線で失敗しやすい点を把握し、自分の理想の家のイメージを明確にしておくことでたいていの失敗は回避することができると思います。
一生一度のマイホーム計画ですから失敗の可能性は少しでも下げたいもの。間取りや生活動線の面でも後悔することのないよう前もってシミュレーションしておくことをオススメします。しっかり勉強して理想のマイホームを手にいれましょう。
「間取りシミュレーション」という言葉にすると少し難しいように考えてしまいがちですが、カンタンな話、いろいろなハウスメーカーのカタログを取り寄せて比較するだけでも立派なシミュレーションになります。
ハウスメーカーカタログにはたくさんの間取りの実例が掲載されています。それらを比較し、気に入った間取り実例があったらスマホでけっこうですので写真を撮っておいてください。気に入った間取りプランをいくつか担当者に見せるだけでも「施主がどんな間取りにしたいか」を汲み取ってくれるハウスメーカーは優秀だと判断していいでしょう。
ハウスメーカーの提案力を測ることもできますので、まずはカタログ一括請求をして好みの間取り実例をたくさん撮り貯めておきましょう。