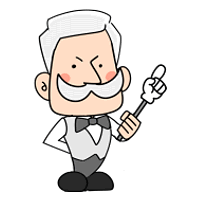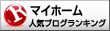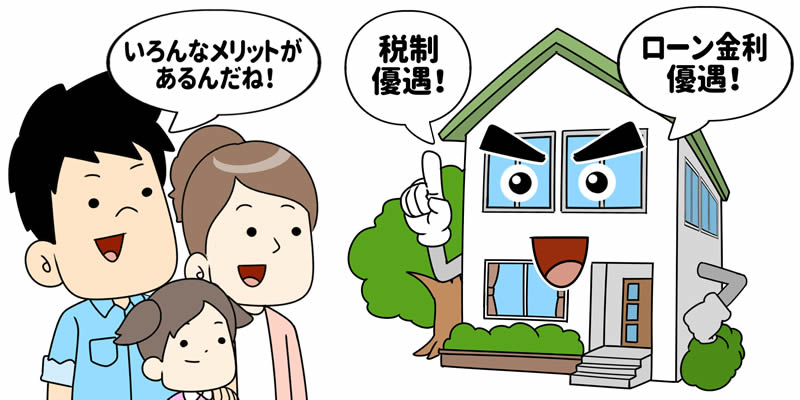
「長期優良住宅」と言う言葉をご存知でしょうか。
おそらくマイホーム購入を検討している方ならば、ほとんどの方が一度は目にしたことがある言葉だと思います。
ですが、その内容についてはあまり詳しくご存知ない方も多いと思います。長期優良住宅とは言葉通り、長期に渡り優良な住まいを維持できるだけでなく、税制面や住宅ローンの金利面などさまざまな面でメリットがあります。しかし、その反面、ランニングコスト面などデメリットとなる部分もありますので、注文住宅を購入しようとする方は長期優良住宅制度について一度しっかりと学んでおくことをオススメします。
当ページでは、長期優良住宅のメリット・デメリットについて詳しくまとめていきます。できるだけわかり易く端的に要点をまとめていきますので、是非ご一読ください。
長期優良住宅とは
まずは長期優良住宅とはなにか?という点について説明していきます。
長期優良住宅とは2009年にスタートした長期優良住宅認定制度の認定基準を満たし「認定」を受けた住宅のことを指します。
数世代に渡り良好な状態で快適に住み続けられるように「バリアフリー性」「可変性」「耐震性」「省エネルギー性(断熱性等)」「劣化対策性」などに優れていることが具体的な条件で、ひらたく言えば「100年単位で長持ちしリフォームもしやすい優良物件である」と国土交通省にお墨付きを貰った住宅ということですね。
長期優良住宅認定を受けることで、数世代に渡り快適に住み続けられる安心を得られるうえ、税制面や住宅ローンの金利面でも優遇されるメリットがあります。
長期優良住宅認定通知書は再発行不可
長期優良住宅認定を受けると「長期優良住宅認定通知書」が発行されます。長期優良住宅認定通知書は税控除を受ける際などに必要となる重要な書類です。注意しないといけないのはこの書類は再発行ができないという点です。大切に保管しましょう。
長期優良住宅の認定基準
長期優良住宅認定を受けるためには、以下の項目を全て満たしている必要があります。戸建て住宅と集合住宅(マンション)で認定基準が若干異なりますので注意しましょう。戸建て住宅の場合は7項目、集合住宅(マンション)の場合は9項目の基準をクリアし各自治体に申請することによって長期優良住宅認定を受けることが可能です。
長期優良住宅の認定基準① 住戸面積
一戸建ては総床面積75㎡以上有すること。また、少なくともワンフロアの床面積が40㎡以上あること。
※ただし地域の実情によっては引き下げが可能。下限は55㎡。
※マンションの場合は55㎡以上。
長期優良住宅の認定基準② 耐震性
極めて稀に発生する大規模地震に対して継続して住むための改修の容易化を図るため損傷レベルの低減を図ること。具体的には「耐震等級2以上」あるいは「免震建築物」であることが認定基準となります。
長期優良住宅の認定基準③ 省エネルギー性
次世代エネルギー基準に適合するために必要な断熱性能などの省エネルギー性能が確保されていること。
具体的には「省エネルギー対策等級4以上」であることが認定基準となります。
長期優良住宅の認定基準④ 劣化対策
通常想定される維持管理条件下で、構造躯体が数世代に渡り(100年程度)使用可能となる措置がとれること。
具体的には床下・小屋裏の点検口を設置し、なおかつ床下には330mm以上の高さが確保されていることが認定基準となります。
長期優良住宅の認定基準⑤ 維持保全計画
定期的な点検や補修に関する計画が策定されていること。
具体的には少なくとも10年に一回は定期点検を実施することが必要となります。また大規模な地震や台風などの天災により被害を受けた場合は臨時点検を実施する必要もあります。
長期優良住宅の認定基準⑥ 維持管理・更新の容易性
基本的に住宅の内装や設備は構造躯体よりも耐用年数が短いです。それらの内装・設備について維持管理を容易に行うために必要な措置が講じられている必要があります。
また点検や補修などの作業時に構造躯体に影響を及ぼさないことも必要です。
長期優良住宅の認定基準⑦ 居住環境
良好な景観の形成、地域における居住環境の維持および向上に配慮されたものであること。
これはちょっと分かりにくいですが簡単にいうと「マイホームを建てる時はその地域の景観に合わせましょう」という話です。
例えば、京都などは歴史的な建造物が多数あることから厳しい景観条例がありますが、そういった場所にはあまりにも奇抜な住宅を建てるのはやめましょう、ということです。一般的な住宅ならほぼ抵触しないので余り気にしないでいいと思います。
長期優良住宅の認定基準⑧ バリアフリー性
長期に渡り住むことが前提の住宅ですので、将来のバリアフリー改修に必要なスペースが確保されていることが必要です。
※ただしこの項目は集合住宅(マンション)だけに必要な認定基準です。戸建て住宅の場合は適用されません。
長期優良住宅の認定基準⑨ 可変性
バリアフリー性と少し通ずる部分がありますが、ライフスタイルの変化に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていることも認定条件の一つです。具体的には配管・配線を変更するために躯体天井高が高く設計されていることが必要です。
※ただしこの項目は集合住宅(マンション)だけに必要な認定基準です。戸建て住宅の場合は適用されません。
長期優良住宅のメリット
長期優良住宅認定を受けると複数のメリットがあります。
もちろん長期優良住宅認定を受けるためには多数の項目をクリアしないといけないため、単純に住宅のクオリティが高いという面や将来的な住宅の資産価値という面でも有利ですが、その他にも税制面や住宅ローンの金利面でも優遇されるというメリットがあります。
この項目では、長期優良住宅認定を受けた際のメリットについてまとめます。
長期優良住宅のメリット① 住宅ローン控除の限度額(控除額)が増える
住宅ローンを利用して不動産を購入した場合、年末ローン残高の1%分の金額が所得税と住民税から10年間 税額控除される住宅ローン減税という制度があります。
住宅ローン減税の最大控除額は一般住宅の場合は年間最大40万円ですが、長期優良住宅の場合は年間50万円となります。10年換算だと一般住宅=400万円、長期優良住宅=500万円と100万円もの差が出ることになります。
10年間で最大100万円も税控除額が変わってくると聞くと非常に差が大きいように感じますが、注意すべきは誰しも最大額の控除を受けられるわけではないという点です。
例えば年末ローン残高が5000万円の場合、一般住宅と長期優良住宅では以下の差が出ます。
一般住宅の場合
5000万円×1%=50万円
最大の税額控除額が40万円なので40万円の税額控除
長期優良住宅の場合
5000万円×1%=50万円
最大の税額控除額が50万円なので50万円の税額控除
この場合は10万円お得になります。(ただ翌年以降は年末ローン残高が減っていくため、ローン返済額に応じて年々、控除額も減っていくので、マックス500万円の税額控除を受けるためには5000万円以上の住宅ローンを組む必要があります)
次は年末ローン残高が3000万円の場合を考えてみましょう。
一般住宅の場合
3000万円×1%=30万円
30万円の税額控除
長期優良住宅の場合
3000万円×1%=30万円
30万円の税額控除
この場合はどちらも控除額が変わりません。
この制度は4000万円を超える住宅ローンを借りた場合や40万円を超える所得税、住民税を納めている人にとっては非常に節税効果が高いですが、住宅ローンの借り入れが4000万円以下の場合はさほど節税効果を発揮しないことを覚えておきましょう。
また、あくまで納める税金(所得税・住民税)に対しての控除ですので、所得税と住民税の合算が年間40万円未満の方は一般住宅でも長期優良住宅でも実質変わりはありません。
※2019年10月01日に予定されている消費税増税後は、住宅ローン控除の控除期間が従来の「10年間」から「13年間」へと引き延ばされます。
※住宅ローン控除の限度額増額措置は令和3年(2021年)までに入居した場合に限ります。
長期優良住宅のメリット② 固定資産税の減額期間が2年延長される
固定資産税は不動産を所有していると必ず毎年かかってくる税金で毎年1月1日時点での不動産の所有者に対して課税されます。
令和2年(2020年)までに新築された住宅ならば一般住宅でも長期優良住宅でもどちらも減税措置がありますが、その期間に差があります。
戸建ての場合
一般住宅の場合 :新築から3年間は固定資産税が2分の1に減額
長期優良住宅の場合:新築から5年間は固定資産税が2分の1に減額
マンションの場合
一般住宅の場合 :新築から5年間は固定資産税が2分の1に減額
長期優良住宅の場合:新築から7年間は固定資産税が2分の1に減額
長期優良住宅の場合は固定資産税の減額期間が2年間延長されるというメリットがあります。
固定資産税は住宅の構造や設備、地価などにより大きく異なるため一概に金額はいえませんが、一般的な30~40坪程度の住宅であれば年間およそ10~20万円程度の固定資産税が課税されます。
減税措置は2分の1ですから、10~20万円の半額と考えると「5~10万円×2年間分=10~20万円程度」の金額が長期優良住宅にするとお得になる計算になります。
※固定資産税額は建物の構造や地価によって異なりますので正確な金額ではありません。
※固定資産税の減額期間の延長は令和2年(2020年)までに入居した場合に限ります。
長期優良住宅のメリット③ 登録免許税が優遇される
登録免許税は不動産を購入した人が所有権を登記する際に、登記手続きで課税される税金です。不動産を購入した場合、必ず管轄法務局にて登記手続きを行う必要があります。
長期優良住宅の場合、この登録免許税も一般住宅に比べて優遇されます。
登録免許税の軽減率は以下の通りです。
| 住宅の種類 | 保存登記 | 移転登記(一戸建て) | 移転登記(マンション) |
|---|---|---|---|
| 一般住宅 | 0.15% | 0.30% | 0.30% |
| 長期優良住宅 | 0.10% | 0.20% | 0.10% |
※登録免許税の軽減は令和2年(2020年)までに入居した場合に限ります。
例えば4000万円の不動産の保存登記をするケースだと以下の計算になります。
一般住宅
4000万円×0.15%=60000円
長期優良住宅
4000万円×0.1% =40000円
20000円お得な計算になりますね。長期優良住宅の認定を受けると、この登録免許税の軽減措置ではおおよそ1~3万円程度の節税が可能と考えておきましょう。
長期優良住宅のメリット④ 不動産取得税が優遇される
土地や建物などの不動産を取得した時は「不動産取得税」という税金も課されます。不動産取得税は土地と建物の取得金額から「控除額」が差し引かれて算出されます。
長期優良住宅は不動産取得税の控除額でも一般住宅よりも優遇されます。不動産取得税の控除額は一般住宅の場合、最大1200万円ですが、長期優良住宅の控除額は最大1300万円となります。
| 住宅の種類 | 不動産取得税の控除額 |
|---|---|
| 一般住宅 | 最大1200万円 |
| 長期優良住宅 | 最大1300万円 |
※不動産取得税の軽減は令和2年(2020年)までに入居した場合に限ります。
長期優良住宅の場合、不動産取得税において最大100万円分の控除額が優遇されるということです。ただしあくまでも「控除額」が増額されるだけであり、実際に支払う税金の差額は数千円程度となるケースが多いです。長期優良住宅は不動産取得税の面でも優遇されますが、そこまで大きな影響があるわけではありません。
長期優良住宅のメリット⑤ 住宅ローンの金利面で優遇される。
長期優良住宅は、住宅ローンを借りる場合の金利面でも優遇されています。
長期固定金利の住宅ローン【フラット35】では、金利面で優遇される【フラット35S】という商品があり、長期優良住宅ではフラット35Sが適用できます。
フラット35Sは耐震性や省エネルギー性などが優れた住宅を取得した場合に適用できる商品となり「金利Aプラン」「金利Bプラン」があります。
それぞれの違いは以下の通りです。
| フラット35Sのタイプ | 特徴 |
|---|---|
| 金利Aプラン | 当初10年金利を0.25%引き下げ |
| 金利Bプラン | 当初5年金利を0.25引き下げ |
金利Aプランは10年間、金利Bプランは5年間0.25%金利を引き下げられるという特徴があります。
例えば3000万円を借り入れた場合のモデルケースの場合、当初10年間は月々の支払いが「6250円」安くなる計算になります。月々「6250円」が10年間優遇されるので、10年間の合計では75万円お得になります。これはなかなか大きな優遇ですね。
ただし、フラット35Sは長期優良住宅でなければ適用できないというわけではなく、耐震性や省エネルギー性などの一定の条件をクリアし性能証明書を取得できるならば、一般住宅でも適用することが可能です。
長期優良住宅のメリット⑥ 補助金が出る可能性がある
長期優良住宅のメリットとして国から補助金が貰える可能性があります。
ただし長期優良住宅を新築した場合に貰える補助金はかなり条件が限られますので、その点は留意しておくことが必要です。
認定長期優良住宅は耐震性や省エネルギー性に優れた住宅を新築する場合は「地域型住宅グリーン化事業」にて補助金が交付される場合があります。補助金の額は以下の通りです。
認定長期優良住宅:上限110万円
※地域材の過半利用の場合 上限20万円加算
※三世代同居対応要件適合 上限30万円加算
ただし、この補助金は条件が厳しくどこのハウスメーカーで建てても貰えるというわけではありません。
地域型住宅グリーン化事業では工務店や建材流通業者が連携してグループをつくり、国に採択されたグループに属する中小工務店で住宅を建てる場合にのみ補助金が出ます。採択を受けたグループは、以下のリンクより確認してください。
また、この「地域型住宅グリーン化事業」の補助金は長期優良住宅を新築した人だけが貰えるというわけではなく「低炭素住宅」の建設でも貰える場合があります。
補助金が出るというのは大きなメリットですが、「ハウスメーカーが限定される」というのは非常に厳しい条件だと思います。当サイトでは「補助金が出るから」という理由だけでハウスメーカーを決めてしまうことはオススメしません。
あくまでも「決めたハウスメーカー・工務店が補助金対象の業者だったらラッキー」という程度に考えておくべきでしょう。
長期優良住宅のメリット⑦ 資産価値の評価が高くなる
長期優良住宅認定を受けることで、将来的に売却する際などは有利になる可能性が高いです。長期優良住宅はそもそも、耐震性や省エネルギー性などさまざまな面で性能が高いことが証明された住宅であり、また住んでからも定期的な点検など性能を維持・保全することが義務付けられているため、一般住宅に比べて資産価値の面でも高く評価されるケースが多いです。
長期優良住宅は将来的に売却する場合も高く評価されやすい、売りやすいなどのメリットがあると言えます。
長期優良住宅のデメリット
次は長期優良住宅のデメリットもみていきましょう。長期優良住宅認定を受けるデメリットはどのようなことが考えられるでしょうか。なにごともメリットがあればデメリットもあるものです。メリットとデメリットをどちらもしっかりと把握し、自分にとってはどちらが有利なのかを考えて判断することが大切です。
長期優良住宅のデメリット① イニシャルコスト(初期費用)が高くなる
長期優良住宅は税制面や金利面などランニングコストで優遇されるという特徴がありますが、その反面イニシャルコスト(初期費用)が高くなる傾向にあります。長期認定住宅を受けるためには住宅のさまざまな性能を向上させる必要があり、建設費自体も一般住宅に比べて10%~20%高くなると言われています。
また長期優良住宅認定を受けるためには各種申請をする必要があり、申請にかかる手数料などのコストが5~6万円程度かかると考えておきましょう。
長期優良住宅認定を受けるデメリットとしてはまずはイニシャルコストの点が一番大きいと言えると思います。
長期優良住宅のデメリット② 維持保全をする必要がある
もう一つ長期優良住宅は、住んでからも「維持保全をしなければならない」点がデメリットとして挙げられます。
長期有料住宅は認定条件の一つに「維持保全計画が策定されていること」が挙げられています。長期優良住宅であることを維持保全するために定期的な点検や補修を少なくとも10年に1度は行う必要があります。もし計画に策定された点検を行われなかった場合は長期優良住宅認定が取り消される可能性がありますので注意が必要です。
長期優良住宅の場合これらの点検・補修等にかかるコスト・手間がデメリットと言えます。
長期優良住宅のデメリットについて補足
長期優良住宅のデメリットの面を少しだけ補足しておきます。前述のデメリット1にて「長期優良住宅の建設費はだいたい一般住宅よりも10~20%高くなる」と述べておりますが、これはあくまでも一般的にそう言われることが多いというだけで、実際「基準となる一般住宅」がどの程度の性能を備えたものなのかは非常にあいまいです。
近年では長期優良住宅認定を受けていなくとも優れた性能を誇る一般住宅はありますし、そういった高性能な一般住宅と比較した場合は建設費がそこまで変わらない可能性も十分あり得ます。
長期優良住宅認定を受けるために建設費がどれくらい高くなるかは一概に比較することが難しい項目ですので詳しくは実際にハウスメーカーに相談したり、相見積もりを取るのが確実です。
また長期優良住宅は「維持保全」の義務があるため、少なくとも10年に一度は点検・補修をすることをデメリットの一つとして挙げておりますが、住宅というものは長期優良住宅であっても一般住宅であっても、少なくとも10年に一度くらいのペースでは点検はする必要があるものです。
一般住宅でも10年に一度くらいのペースで点検は入れるケースがほとんどだと思いますので、明確なデメリットというほどでもないと思います。
あくまで「維持保全(点検・補修)」が義務化されているか、そうでないかの違いと考えるべきでしょう。
長期優良住宅 一般住宅 比較一覧表
わかりやすく比較しやすいように長期優良住宅と一般住宅の違いを一覧にまとめておきます。
| 異なる点 | 一般住宅(戸建て) | 長期優良住宅(戸建て) |
|---|---|---|
| 住宅ローン控除の限度額 | 400万円 | 500万円 |
| 固定資産税の減額期間 | 3年間 2分の1に減額 | 5年間 2分の1に減額 |
| 不動産取得税の控除額 | 最大1200万円 | 最大1300万円 |
| 登録免許税 | 保存登記0.15% 移転登記0.3% |
保存登記0.1% 移転登記0.2% |
| フラット35の適用 | 特に規定なし | 金利を0.25%引き下げ(当初10年) |
| 建設費 | – | およそ10~20%高くなる傾向 |
| 維持保全 | 義務なし | 義務あり(10年に一度の点検・補修) |
長期優良住宅のメリット・デメリット まとめ
長期優良住宅のメリット・デメリットについては以上となります。ご理解いただけましたでしょうか。皆様のマイホームプランのお役に立てて頂ければ幸いです。
最後にまとめますが長期優良住宅には多数の税制面・金利面でのメリットがありますが、その恩恵を最大限に受けることができるケースは限られるということです。実際「あえて長期優良住宅の認定は受けない」という施主やハウスメーカーもたくさんおります。
大切なのは「自分の建設プランではどちらが総合的にお得か?」という点を正確に把握することです。
あくまで自分の検討しているプランで長期優良住宅にした場合と一般住宅にした場合でどれくらいイニシャルコストに違いが出てくるのか、どれくらいランニングコストで違いがでてくるのか?総合的なコストを把握し判断することが大切です。
実際にどれくらいの金額がお得になるのか?という点に関しては、一概には比較することができませんので、必ず事前にハウスメーカーと相談するか相見積もりを取りましょう。
まずは希望の予算・エリアに対応しているハウスメーカーを何社か見つけることから始めましょう。せっかく相見積もりをするなら性能スペックやデザインが希望条件にある程度あてはまらないとあまり意味がありません。
そこで最初のふるい落としに役立つのが「住宅カタログ」です。何冊かカタログに目を通すだけで各ハウスメーカーの特徴・強みがだいたいわかってきます。何社かお気に入りをみつくろったら「あいみつ」を取ってみてください。
似たようなスペックでも「ハウスメーカーごとにこんなに価格が違うの?!」と驚くと思います。価格差を知らずになんとなく決めてしまってたら…ゾッとしますね。すごくカンタンな作業ですが、これをやるかやらないかでマイホーム計画の失敗率は格段に下がります。「カタログ比較」は注文住宅の登竜門。まずはライフルホームズから始めましょう!